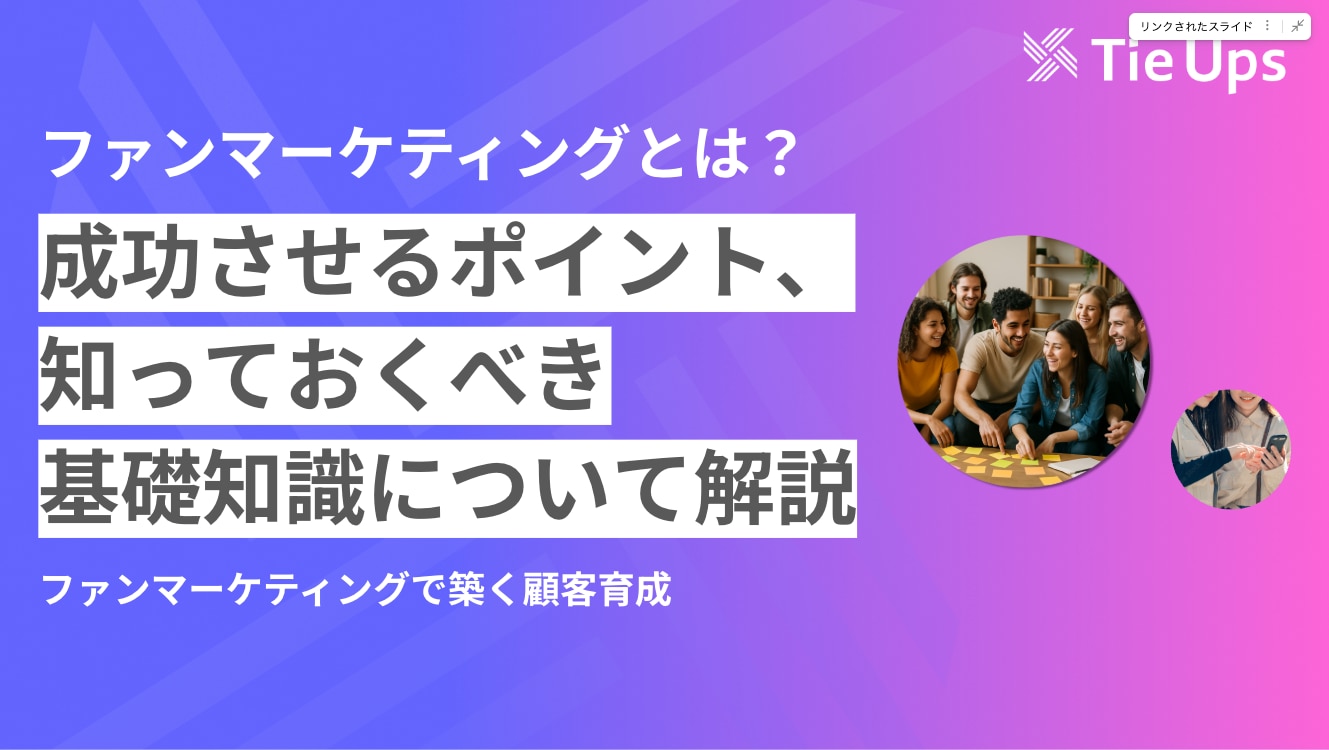
ファンマーケティングとは?成功させるポイント、知っておくべき基礎知識について解説
消費者の価値観や購買行動が多様化する中、単なる「売る」ためのマーケティングでは限界が見え始めています。そこで今注目を集めているのが、ブランドや商品に共感し、応援してくれる“ファン”との関係を深め、その熱量をビジネス成長の原動力に変える「ファンマーケティング」です。
本記事では、なぜいまファンマーケティングが必要なのか、その効果や実践ポイント、そして成功に導くための最新手法までを解説します。
目次[非表示]
- 1.ファンマーケティングとは?
- 2.なぜファンマーケティングが注目されているのか?
- 3.ファンマーケティングのメリット
- 4.ファンマーケティングの注意点
- 5.ファンマーケティングを成功させるには
- 5.1."共感"を起点に設計
- 5.2.ファンの行動を"可視化"して設計に反映
- 5.3.継続するための社内体制と評価軸を持つ
- 6.ファンマーケティングを成功に導くツール
- 7.なぜ「コミュニティプラットフォーム」ファンマーケティングの成功に鍵を握るのか?
- 8.TieUpsが提唱する「推し行動促進マーケティング」とは?
- 8.1.推し行動促進マーケティングのメリット
- 8.1.1.顧客の推奨行動を可視化できる
- 8.1.2.共感ベースの自発的アクションを引き出す
- 8.1.3.自然拡散型の“語られるブランド”を育てられる
- 8.1.4.ユーザーとの関係性を“経営視点”でマネジメント
- 8.2.このような課題をお持ちの方は、ぜひ資料請求を
ファンマーケティングとは?
ファンマーケティングとは、ブランドや商品に強い愛着・共感を持つ顧客(=ファン)と継続的な関係を築き、その熱量をマーケティング資産として活用する戦略です。
ファンマーケティングの本質は、「購買行動の最適化」ではなく、「ブランドとの関係性を設計すること」にあります。
「共感したから拡散したくなる」「好きだから人に薦めたい」
このような感情の変化を設計・可視化し、継続的に強めていく仕組みこそが、現代のマーケティングに求められるものです。
なぜファンマーケティングが注目されているのか?
かつては、大規模な広告やキャンペーンで話題を生み出すことが可能でしたが、現在、消費者の行動や価値観は大きく変化しており、その変化に合わせたマーケティングが必要となります。
もちろん、「ファンを大事にすること」が大事なのは昔から分かっていたことかもしれません。しかし、それが“戦略の中心”にまで押し上げられているのが、いまのマーケティングのリアルです。
ここでは、ファンマーケティングが注目されている理由を3つの観点から整理してみます。
顧客獲得コストの高騰
近年、リスティング広告やSNS広告などの入札単価が上昇し続けており、新規顧客の獲得コスト(CAC)は過去5年で約60%増加したとされています(HubSpot調査)。
これは、まず第一に、広告出稿の競争が激化している点が挙げられます。特にD2CブランドやSaaS企業など、デジタルに強いプレイヤーが増えたことで、限られたターゲットユーザーを巡る入札競争が過熱し、クリック単価(CPC)や獲得単価(CPA)が高騰しています。
また、プライバシー保護の強化に伴うターゲティング精度の低下も大きな要因となっています。Google ChromeのサードパーティCookie廃止などの影響で、従来のような精緻なユーザー追跡が難しくなっています。これにより広告の配信効率が落ち、以前と同じ成果を出すために、より多くの予算を投じる必要が生じています。
その一方で、既存顧客の維持・アップセルは約5分の1のコストで済むとされており、「新規よりファンを育てる」戦略が見直されているのです。
口コミなどのUGCの重要性の拡大
消費者はブランド発信の広告よりも、ユーザー発信の投稿やレビュー(UGC)を信頼しています。Nielsenの調査では、消費者の92%が「知人の推薦を最も信頼している」と回答しています。
これは消費者の信頼の拠り所が企業から一般ユーザーへと移行している点が挙げられます。スマートフォンとSNSの普及によって誰もが発信者になれるため、企業の宣伝よりも、実際に商品やサービスを利用した人のリアルな声が現代では重視されます。
これに伴い、企業はユーザーに自然なかたちで投稿してもらう仕組みづくりに力を入れています。また、Googleなどの検索エンジンやSNSのアルゴリズムにおいてもUGCは評価されやすく、継続的な投稿がSEOにも好影響を与えます。
”モノ”消費から"コト”消費、そして”トキ”消費へ
Z世代・ミレニアル世代を中心に、単なる機能や価格だけでなく、ブランドの思想・ストーリーに共感するかどうかが購買理由として重視されるようになっています。実際、ブランドの価値観と自分の価値観が合わないと購入を躊躇すると回答したZ世代は92 %にのぼり、76 %もの若年層が「ブランドは社会的使命を持つべき」と考えているという調査結果もあります。
かつては商品の性能や価格といった“モノそのものの価値”が購買の決め手となっていましたが、モノが溢れる現代においては、商品自体の機能的な価値よりも、その商品を通じて得られる“体験”や“感情的なつながり”が重視されるようになっています。
たとえば、単に飲み物を買うのではなく、「誰とどんなシーンで楽しんだか」といったストーリーや体験に価値を感じるようになってきているのです。こうした背景においては、ユーザー自身が体験を語り、共有するUGCが非常に相性が良く、その発信が他の消費者の共感を呼び、さらなる体験や共鳴の連鎖を生むという循環が生まれます。
また、近年ではコト消費に変わる”トキ”消費と呼ばれる「その時・その場でしか味わえない盛り上がりを楽しむ消費」という概念があらたに提唱されています。
トキ消費という言葉は博報堂生活総合研究所が2017年頃に提唱した消費行動で、スマホなどのモバイル機器やSNSの普及により、いつでもどこでも不特定多数の人とつながれる現代では、時や場所を共有することが容易になりました。そこで消費者は共通のテーマや趣味・趣向を持つ者同士でそのテーマに沿ったイベントなどに参加し、ほかの消費者と一緒に盛り上がって楽しむ体験に価値を感じるようになりました。
トキ消費の代表例は「アイドルやアーティストライブ」「映画の応援上映」「ワールドカップ観戦」「ファンミーティング」などが挙げられ、どれも「その時」「その場所」でしか味わえないといった共通の特徴があります。
企業も単に商品を売るのではなく、ユーザーとの感情的な関係性を築き、“共に物語をつくる存在”としてファンと関わることが、ブランド価値の源泉となりつつあるのです。
ファンマーケティングのメリット
近年のユーザーは、広告を見たからといってすぐに商品を購入するわけではありません。気になる情報に触れたあと、自ら検索し、内容を比較・検討し、ようやく行動に移し、場合によってはその体験を誰かにシェアするといった流れが当たり前になっています。
これは「AISASモデル(Attention → Interest → Search → Action → Share)」としても知られる購買行動プロセスですが、ファンマーケティングはまさにこの流れを自然かつ継続的に生み出す土壌を育てる仕組みです。広告とは異なり、ファンの“共感”や“熱量”が起点となることで、ユーザーの行動はよりリアルに、そして強くブランドと結びついていきます。
ここでは、そんなファンマーケティングの3つの代表的なメリットを、ユーザー行動の変化に着目しながらご紹介します。
広告に頼らず“売れる”仕組みがつくれる
ファンマーケティングでは、ブランド側の情報発信だけでなく、ファン自身の発信が新たなユーザーの関心を生む出発点になります。たとえば、商品を使ったファンが「すごくよかった」とSNSに投稿します。すると、その投稿を見た他のユーザーが「なんだろう?」と興味を持ち、自然と調べはじめる流れを作ることができます。
このように、ファンの“シェア”が他のユーザーの“注意”や“検索”の導線になり、さらには購入や体験へとつながっていく..といったAISASモデルの流れを、ブランド主導ではなくユーザー主導で回しているのが特徴です。
さらに、このようなユーザー発信の情報は、企業の広告よりも信頼されやすく、コンバージョン率にも好影響を与えます。広告費に頼らず、“売れる”状態をファンの力で継続的に育てることができるのです。
ユーザーから”ブランドの味方”へ
商品やサービスに対して関心を持ったユーザーが、さらにそのブランドに参加・関与できる機会を持つことで、行動の熱量がぐっと高まります。たとえば、ファン限定の体験イベントや、意見が反映されるキャンペーン、ミッション型の投稿施策などは、ただの購入体験とは異なる“心理的参加”を生み出します。
こうした体験を通じて、ユーザーは「自分もこのブランドの一部だ」という帰属意識を持つようになり、やがては他の人にその魅力を伝えるようになります。自ら進んで発信し、応援する“ブランドの味方”へと進化していくのです。
"リアルな声"が集まりやすくなり、商品や施策改善につながる
ファンとの関係性が深まるほど、企業に対する発言のハードルは下がり、率直で具体的なフィードバックが集まりやすくなります。たとえば「もっとこうしてほしい」「こういう使い方が便利だった」など、商品開発やUI改善につながる意見がファンから自然と届くようになります。
これは、ユーザーが「情報を集め(Search)」「体験し(Action)」「共有する(Share)」という一連の行動の中で感じたリアルな温度感が含まれているからこそ得られるものです。加えて、企業側がその声に応え、改善策を打ち出すことで、ファンとの信頼関係はさらに強固なものとなります。
このような双方向の関係性が築かれると、ファンの中でも「このブランドは自分たちの声を聞いてくれている」という満足感が生まれ、それが次なるシェアや応援の起点になっていきます。単なるクチコミ以上の、ブランド共創型の好循環がここに生まれるのです。
ファンマーケティングの注意点
ファンマーケティングは、うまく設計すればブランドにとって非常に心強い武器になりますが、実際にやってみると、「思ったよりうまく育たない」「成果がよくわからない」と感じる場面も多くあります。
特に初期段階では、即効性を求めすぎると逆に失敗しやすいのがファンマーケの難しいところです。
ここでは、取り組む前にぜひ押さえておきたい、2つの注意点をご紹介します。
ファン育成は中長期的に実施していくもの
ファンマーケティングは、短期的な売上をつくるための施策ではありません。
ミッションを1つ用意したからといって、すぐに投稿が増えたり、コミュニティが活性化したりするわけではなく、“信頼を積み上げる”地道なフェーズが必ず必要です。
最初のうちは、動きが地味に見えるかもしれません。でも、その静かな立ち上がりこそが、長く続くファンベースの土台になります。
焦って早く結果を出そうとすると、企業主体の押しつけ感が強くなり、逆にファンの熱が冷めてしまうことも。
半年〜1年といったスパンでじっくり設計していくことが、ファンマーケティングの成功ポイントになります。
成果が見えにくく、投資対効果が分かりにくい
ファンマーケティングでは、「売上○円UP」や「CVR○%改善」といった明確な成果が出にくく、体感では盛り上がっていても、それを数字で説明するのが難しいという課題があります。
SNS投稿やコミュニティ参加などの行動は、定量的な売上にはすぐにはつながらず、“応援の気持ち”のような定性的なものにとどまるケースも多いです。
だからこそ、「ファンの声が集まり始めている」「参加率が上がってきている」など、プロセスの変化にも目を向けて成果を評価する視点が必要になります。
ファンの行動を可視化できるツールや、スコアリング・参加ログなどを活用することで、「手応えがないからやめよう」ではなく、「今は育成フェーズ」と割り切って続けられる設計をしておくと安心です。
ファンマーケティングを成功させるには
ファンマーケティングには即効性がないぶん、どう育て、どう継続するかが成果を大きく左右します。
「応援したくなる仕組みがあるか?」「ちゃんとファンの声が届く設計になっているか?」といった、人の気持ち”に寄り添う工夫がとても重要です。
ここからは、ファンマーケティングを形だけで終わらせず、ブランドの強みとして根づかせていくための実践ポイントをいくつかご紹介します。
"共感"を起点に設計
ファンマーケティングの原点は、そのブランドや商品に“共感”できるかどうかです。
商品の機能や価格だけではなく、「なぜこのブランドを応援したくなるのか?」というストーリーや価値観に共感してもらうことが、行動につながります。
たとえば、以下のような要素は共感を生み出す起点になります
- ブランドの背景や創業ストーリーの発信
- ユーザー参加型の「共創プロジェクト」
- 商品ではなく“人”や“考え方”が見える投稿
共感を軸にした設計は、一時的な注目よりも深い支持を生む仕組みになります。
ファンの行動を"可視化"して設計に反映
ファンはただ「好き」と思っているだけではなく、応援したい気持ちを“行動”で示してくれる存在です。
その行動(投稿・参加・紹介など)をきちんと可視化し、データとして蓄積・活用することで、ファンの熱量や関心の変化を読み解くことができます。
具体的な可視化のポイントは
- ミッション参加率、継続率
- 投稿数、ハッシュタグ利用数、いいね数
- ログイン頻度やアクティブ時間帯
- フィードバックやアンケートの声
このような定量+定性のデータをもとに、「次に何を提供すれば喜ばれるか?」をファンのリアルな動きから設計していくことが重要です。
継続するための社内体制と評価軸を持つ
ファンマーケティングは「継続」が命です。
だからこそ、施策の打ちっぱなしや思いつき運用ではなく、継続可能な運用の型を持つことが成功の前提になります。
そのためには、以下のようなポイントを意識してコミュニティを設計しましょう
- 月次やクォーター単位でのミッション設計/振り返り
- 「熱量のような定性KPI」と「売上などの定量KPI」を分けて評価する視点
- ミッション/投稿/アンケートなどのサイクル運用
- 応援してくれるファンへの「還元設計」も定常化
継続のなかで、徐々に“応援の文化”がブランドの中に根づいていくことを目指すのが、ファンマーケティングの理想的なゴールです。
ファンマーケティングを成功に導くツール
ファンマーケティングを始める目的や意義は、多くの企業に浸透しつつあります。実際に「共感の醸成」「顧客ロイヤルティの向上」「ファン起点のクチコミ拡散」といった成果を期待して取り組む企業も増えています。
しかし、いざコミュニティを始めようと思った時に
「具体的に何から始めればいいのかわからない」
「キャンペーンを実施しても継続性がない」
「ファンとの関係性が深まっている実感が持てない」
こういった声をよく耳にします。
こうした課題の多くは、「ツールの選定と設計」に起因しているケースが少なくありません。
ファンマーケティングは、感覚的な“盛り上げ施策”に見える一方で、実はきわめて高い設計力と運用体制が問われるマーケティング手法です。そして、その成功の可否を左右するのが、どのようなツールを使い、どのように自社の施策と組み合わせていくか、という点にあります。
「SNS運用・メール配信」:情報発信とエンゲージメントを高める
ファンとの接点を日常的に生み出すためには、情報発信の設計が欠かせません。とりわけ、SNSやメールはファンに対してダイレクトにコミュニケーションを届けられる手段として、多くの企業で活用されています。
SNS運用ツール(例:Hootsuite、Bufferなど)を導入すれば、複数のSNSアカウントの投稿を一元管理できるだけでなく、ファンの反応やエンゲージメント率の可視化にも役立ちます。また、キャンペーン時には事前に投稿スケジュールを設計し、自動配信することで運用負荷を大きく軽減できます。
一方で、メール配信ツール(例:Mailchimp、Klaviyoなど)は、ユーザーセグメント別にパーソナライズされた情報を届けるのに最適です。開封率やクリック率を元に、配信内容やタイミングを最適化することで、ファンとの信頼関係を段階的に育てていくことができます。
「アンケート・UGC収集」:ファンの声を収集する
ファンマーケティングは、企業が一方的にメッセージを発信するだけでなく、ファンの“声”を起点に共創していくプロセスが重要です。そのためには、ファンのインサイトやアイデア、満足度、要望といった「ファンの内面」を可視化できるツールが必要です。
アンケートツール(例:Google Forms、SurveyMonkeyなど)は、新商品の企画段階でのヒアリングや、サービス満足度調査などに活用できます。特に、定量的なデータだけでなく、自由記述の声を分析することで、定性面での気づきを得ることも可能です。
さらに、UGC(ユーザー生成コンテンツ)収集ツール(例:YOTPOなど)を活用すれば、ファンが自発的に投稿したレビューやSNS写真を収集・整理できます。これらは他のユーザーへの信頼性の高い推薦情報となり、“ファンの声をマーケティング資産として活用する”という視点で非常に効果的です。
「CRM・BIツール」:試作の成果を可視化する
ファンマーケティングの成果を正しく評価し、次の改善につなげるためには、データ分析の視点が欠かせません。ただ「ファンが増えた」ではなく、「どの施策がどんなファンの行動につながったか」「最もLTVが高いのはどの層か」を把握することで、施策の再現性や精度が大きく変わってきます。
CRMツール(例:Salesforce、HubSpotなど)は、ファンごとの行動履歴や属性、購入データなどを一元的に管理できます。これにより、リピーターと新規層を明確に分けた施策や、熱量別のセグメントマーケティングが可能になります。
加えて、BIツール(例:Looker、Tableauなど)を用いれば、施策ごとの成果をダッシュボードで可視化したり、過去のトレンドと比較しながら次のアクションを判断したりできます。施策のKPIを定めた上でのPDCA運用を加速させるうえで、非常に有用なツール群です。
なぜ「コミュニティプラットフォーム」ファンマーケティングの成功に鍵を握るのか?
ここまで紹介してきたツールはいずれも、ファンマーケティングの実施において欠かせない役割を果たします。情報発信、ファンの声の収集、行動の促進、そしてデータの可視化など、それぞれに特化したツールを活用することで、施策ごとの最適化は可能になります。
しかし一方で、それらのツールがバラバラに導入・運用されていることで生まれる課題も見逃せません。
たとえば、
- SNSは盛り上がっているが、そこで得た熱量をどこにも蓄積できない
- アンケートで声を集めても、その声をどう活かせば良いかが曖昧
- ファンの可視化はできたが、一方的な販促活動で終わってしまう
このように、ファンとの関係性が“点”のままでは、ファンマーケティングの本質である「継続的な関係性の構築」は難しくなります。
そこで重要になるのが、「コミュニティプラットフォーム」の存在です。
コミュニティプラットフォームとは、ブランドとファンが継続的につながるためのオンライン上の場であり、ファン同士の交流・意見交換・参加型企画などを通じて、ブランドとの関係性を深めることができる空間です。ここでは、情報発信だけでなく、アイデア投稿、クチコミの共有、限定イベントへの参加、コンテンツの共創など、さまざまな「双方向の体験」が生まれます。
また、単にファンが「聞き手」として存在するのではなく、ブランドの活動に主体的に関わる「共創パートナー」としての関係性を築くことができる点が、大きな特長です。
さらに、
- ファンの行動履歴や熱量の可視化や分析
- カテゴリごとのコミュニティケーション設計
- エンゲージメントを高めるインセンティブ設計
なども統合的に行えるため、点在していたツールや施策を“面”としてつなぎ、ファンとの中長期的な関係性を築くためのインフラとして機能します。
つまり、これまで見てきた各種ツールはあくまで「点」であり、それらを面として束ね、ファンとの関係性を育てる土壌として機能するのがコミュニティプラットフォームなのです。
TieUpsが提唱する「推し行動促進マーケティング」とは?
弊社TieUpsが提唱する推し行動促進マーケティングは、「ユーザーの応援や推奨行動」をAIでスコア化し、企業と顧客のエンゲージメントを可視化・促進する新しいマーケティング手法です。
従来の「参加型コミュニティ」にとどまらず、ファンが自発的に発信・推奨したくなる仕組みを通じて、理念共感を起点に、行動と感情が循環する“共創”の関係を築きます。

単なる“数字”ではなく、「このブランドを応援したい」「この取り組みに共感したから行動したい」という感情の納得感を尊重した、新時代の顧客関係設計です。
推し行動促進マーケティングのメリット
顧客の推奨行動を可視化できる
SNS投稿やレビュー、友達紹介など、ユーザーの応援・共感の行動を「スコア」として見える化できるため感覚に頼らず、施策の効果を明確に把握でき、レポートや意思決定の精度も向上します。
共感ベースの自発的アクションを引き出す
報酬目的ではなく、ブランドの理念や世界観に共感したユーザーが「応援したいから動く」仕組みを実現。企業と顧客の間に、継続的な信頼関係とエンゲージメントが生まれます。
自然拡散型の“語られるブランド”を育てられる
広告に頼らず、ブランドに共感したファンが自らの言葉でサービス価値を発信するため、信頼性の高い推薦が口コミとして広がり、広告費に依存しないブランド成長基盤が築けます。
ユーザーとの関係性を“経営視点”でマネジメント
どんな行動を促し、どういう結果を目指すかを企業側も意識することで、コミュニティ施策が「運用」から「戦略」へと進化。熱量や信頼を中長期的なブランド資産として活用できます。
このような課題をお持ちの方は、ぜひ資料請求を
以下のような悩みがある方には、アクションスコアマーケティングが非常に効果的な戦略となります。
- ファンとの関係性を可視化できず、成果の実感がない
- コミュニティ運用が「場作り」で止まっている
- 広告費に頼らない形で情報拡散したい
- ユーザーの熱量やエンゲージメントを、経営目線で評価・活用したい
- ブランドの理念やストーリーをもっと深く届けたい
- “応援される企業”を目指したいが、仕組みがない
アクションスコアマーケティングは、理念 × 行動 × 可視化の三位一体で、マーケティングを根本から進化させるソリューションです。
資料では導入事例やスコア設計のポイントも紹介しています。気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。




