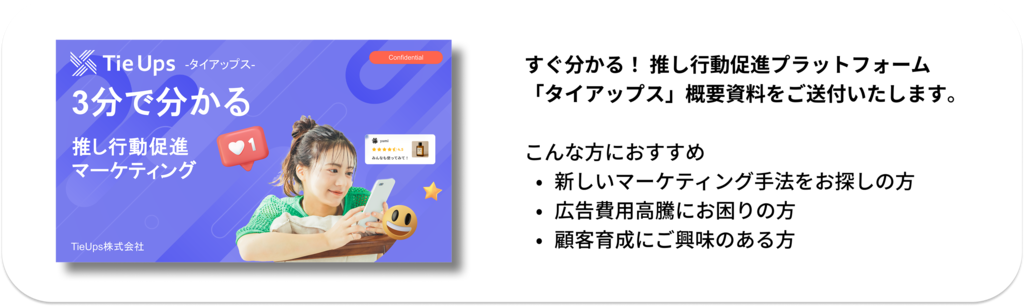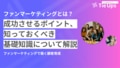この先10年顧客リソース活用がマストになる理由
〜すべての会社がオウンドメディアやSNSを活用する時代のその先へ〜
TieUps株式会社 CEOの小原史啓です。
タイアップスではコミュニティとAIを活用し、企業の“推される力”を可視化し、マーケティングに活かす」ことを目指し、ファンの行動データをスコアリングする仕組みを提供しています。
SNSやオウンドメディアなど、企業が“自前のメディア”を持つことが当たり前になったいま、この先10年を考えると自社のリソース活用だけなく、顧客とどう向き合い顧客のリソース(応援や協力)が得られるかどうかが、マーケティングの成否を分ける差になっていると思います。
今回は「顧客リソースを活用するマーケティング」について、過去の歴史の整理からこの先10年のあるべき姿について考えました。
なぜ顧客リソースの活用が必要なのか?

なぜ今、「顧客リソース」なのか?
「顧客リソースの活用」は、商品やサービスを購入した顧客の行動を通じて、企業の価値創出に貢献してもらうという考え方です。 たとえば、飲食店を利用したお客様がGoogleマップにレビューを投稿する行為は、MEO対策として機能し、次の集客へとつながります。
顧客がマーケティングの一部として機能するという構造は、もはや特別なことではありません。この前提に立った戦略設計が、いま必要とされています。
背景には、広告費の高騰があります。新規顧客を獲得するためのコストは年々上昇しており、広告に依存したモデルでは費用対効果の面で限界が見え始めています。さらに、オウンドメディアやSNSの活用が一般化し、企業間での情報発信力に大きな差がつきにくくなっています。
だからこそ、顧客の行動を資源と捉え、持続的に活用する視点が、これからの戦略において必須になるのです。

顧客は消費者から共創パートナーへ——活用の必然性
顧客との関係性は時代とともに変化してきています。
1980年代までは、顧客は商品を消費する「消費者」として捉えられていました。 大量生産大量消費自体の消費者とはポテトチップスのCMを見て購入し、「食べて袋を捨てる」だけの存在でした。
その後、「生活者」という概念が登場し、マーケティングでは顧客が暮らしの中で商品をどう使い、どう生活を嗜むのか、消費行動の前後も含めて生活価値に注目が集まるようになりました。 企業は単に商品の機能や価格だけでなく、ライフスタイル全体に寄り添う提案を行うことが重視されていったのです。
現在では、顧客は単なる消費者を超え、レビューやSNSでの紹介、友人へのおすすめなどを通じて、ブランドと共に価値を創り出す「共創パートナー」へと変わりつつあります。
加えて、「商品を選ぶ」ことの意味はかつてないほど重くなっています。情報と選択肢があふれる中で、顧客の購買行動は単なる消費を超え、ブランドへの「投票」としての性質を帯びています。
この変化により、企業は一方的に選ぶ側であるだけでなく、選ばれる側として、顧客の声や行動を戦略的に活用し、価値を循環させ共創していくことが不可欠になっています。
広告費の高騰とポートフォリオ分散の必要性

広告効率は進化したのに、なぜ企業の負担は軽くならないのか?
2025年の今、AIやデータ活用の進化によって、広告の「効率」は確かに良くなっています。たとえば、自分の興味やタイミングにぴったり合った商品が表示される体験は、日常的になりました。マーケターの業務効率も向上し、消費者の購買体験もスムーズになっているのは間違いありません。
しかし一方で、企業が支払っている広告コストはむしろ増加傾向にあります。
日本における広告費の推移を見ると、2012年から2022年の10年間で、マス広告(テレビCM・新聞・雑誌など)は約2割減少しましたが、ネット広告は約3.3倍に増加。ついにはネット広告がマス広告を上回る規模になりました。
広告の配信方法は進化したのに、企業の負担は軽くなっていない。むしろ、効率化されたがゆえに「打てる施策が増えた」ことで、総コストが積み上がっている。だからこそ、広告依存だけではなく、顧客リソースを活用した持続的な成長戦略が求められているのです。
細分化とDXの裏で、増え続けるマーケティングコストの実態
ネット広告の成長は、広告の効率化をもたらしたように見えます。実際、DSP広告やターゲティング広告、インフルエンサー施策など、手法は多様化し、それぞれの精度も上がってきました。けれども、それに伴って関係者の数や運用体制はどんどん複雑になっています。
かつてのテレビCMのように「一度に広く届ける」方法と違い、今のネット広告は、複数の小さな施策を積み重ねていく構造。その結果、個別の施策効率が高くても、人件費や間接コストが増え、トータルの負担はむしろ大きくなっているのが現実です。
また、AIやDXの進展によって広告が劇的に効率化するという期待も、現時点では楽観的すぎるかもしれません。実際には、広告の設計・運用がより複雑になり、むしろコストは増える傾向が続いています。
この状況は、今後10年、20年続く可能性が高いと感じています。
過去から考える、この先10年

自社リソースの活用も限界へ——次に備える時代の転換点
過去40年のマーケティングを振り返ると、1980〜90年代はテレビCMや雑誌広告といった“他社リソース”を使う「マス広告の時代」でした。
その後2000年代以降は、自社のWebサイトやオウンドメディア、SNSを使った「自社リソースの時代」へと移り変わっていきました。
多くの企業が、広告費の高騰に対応するためにオウンドメディアやYouTube、SNSといった自社チャネルを活用し、ポートフォリオの分散を図ってきました。
しかし近年では、こうした自社リソースの活用も頭打ちになりつつあります。
競合他社も同様の施策を行う中で、差別化が難しくなり、広告費の上昇も続いています。
広告費は上がり続け、自社リソースは使い切った。そんな現状において、さらなる効率化や競争優位のためには、顧客リソースをどう活用するかが次の10年の成長を左右する鍵になるのです。

顧客とともに広げるマーケティング
次の10年のマーケティングにおいて、重要なリソースとして注目されているのが、AIと顧客リソースの活用です。
皆様の企業が持つ顧客リストは、数万人、数百万規模の場合もあり、その顧客一人ひとりが協力してくれれば、非常に大きなリソースとなります。
過去20年は顧客リソースが十分に活用されていませんでしたが、広告費高騰と自社リソースの限界を考えれば、顧客リソースの活用は自然な次の一手だと考えています。
この先10年、20年で必要になるのは、AI技術を活用しつつ、顧客のリソースをいかに可視化・活用していくかということです。
企業と顧客が共にブランドを広め、共創していくことは、これからのマーケティングにおいて避けられないスタンダードとなっていくと考えています。
TieUpsが考える顧客リソースとの向き合い方
顧客は“使うリソース”ではなく、共に歩む存在
まず大前提として、私たちは「顧客リソースを活用する」という考え方を、企業の内側での戦略概念としては有効と考えていますが、それをそのままお客様に向けて伝えるべきではないと考えています。
顧客は選択の自由を持ち、無数の選択肢の中からその商品やブランドを選んでくださっています。そんなお客様に「何かをしてもらう」ことを当然と考えるのは、根本的に筋が通りません。
あくまで主導権は顧客にあり、企業はその信頼を損なうことなく、共に価値を創っていくスタンスが必要です。

「共創」と「推し活」——顧客との新しい関係性
顧客リソースをどう捉えるか。その前提として、私たちは顧客との関係性を「共創」と「推し活」という2つの視点で見ています。
共創マーケティングは、企業と顧客が同じ目的を持ち、協力し合う関係性です。
たとえば、あるサービスが社会にとって必要だと感じた顧客が、自らその普及に協力してくれる。共感が原動力となる、建設的で目的志向の関係です。
一方の推し活マーケティングは、より情緒的な関わり方です。
製品やブランドに対する「好き」という感情が、購入や紹介といった自発的な行動につながっていく。そこに特別な報酬がなくても、人は動く。これは、経済的合理性を超えた“応援の力”とも言えるでしょう。
この「好きだから勧めたい」という行動は、企業にとって非常に大きな意味を持ちます。なぜなら、インセンティブがなくても顧客が自ら動くことで、マーケティングコストをかけずに波及が起きていくからです。
実際、アニメとコラボした鉄道会社にファンが殺到するように、企業がリソースを追加投下しなくても広がるマーケティングの仕組み。これは、かつては“奇跡”に近いものでしたが、今では多くのブランドで現実に起こっています。
「ファンの力」を可視化し、再現する仕組みづくり
「推し活」のような顧客の熱量ある行動は、決して奇跡ではありません。私たちは、その力を“偶然”ではなく“仕組み”として再現できると考えています。
これまで多くのプロジェクトで分かってきたのは、どんな商品・サービスにも、実は“応援したいと思っている人”が必ず存在するということ。たとえ今は声を上げていなくても、行動につながる可能性を持ったファンは、すでに顧客の中にいます。
私たちは、そのような潜在的ファンを見つけ出し、適切な働きかけで「応援したい」を「行動」に変えていく仕組みを構築してきました。
その具体的な取り組みが、私たちが開発している 「推し行動促進マーケティング」 です。
これは、企業が期待する顧客行動をあらかじめ定義し、それに近いアクションをAIで自動的に点数化・可視化する技術です。
たとえば、特定の季節に合わせた投稿や、ブランドの世界観に合うコンテンツなど、従来なら人力では追いきれなかった“応援行動”を定量的に評価し、活用可能にしていきます。
すでに一部の企業様とこの仕組みを実運用しており、ファンの力を「資産」として活かすフェーズに入っています。

顧客リソースの活用を、仕組みで再現可能に
顧客リソースの活用という考え方は、これまで非常に定性的で曖昧なものでした。口コミや推奨行動のように、企業側が完全にコントロールできず、マネジメントもしづらい。だからこそ「偶然に頼らざるを得ない」というのが、これまでの状況だったと思います。しかし今後の10年は、この“曖昧さ”を克服し、顧客リソースを戦略的に活用できる企業だけが競争優位を築いていけるはずです。
私たちは、この“曖昧さ”に対して技術的な解決を試みています。顧客の「推し」行動をデータとして捉え、スコアリング化することで、より具体的に、そして再現可能な形で顧客リソースを抽出・活用する仕組みを構築しつつあります。
顧客リソースは、企業の“応援される力”です。そしてそれは、商品力やコンセプトだけではなく、関係性や物語、姿勢に宿るものです。この力こそが、次の10年における企業成長を左右するリソースだと考えています。
私たちのシステムでは、こうした「顧客の力」を可視化し、マーケティングに活用する仕組みを提供しています。顧客リソースの活用にご関心のある企業様は、ぜひ問い合わせフォームから資料のご請求をいただければと思います。