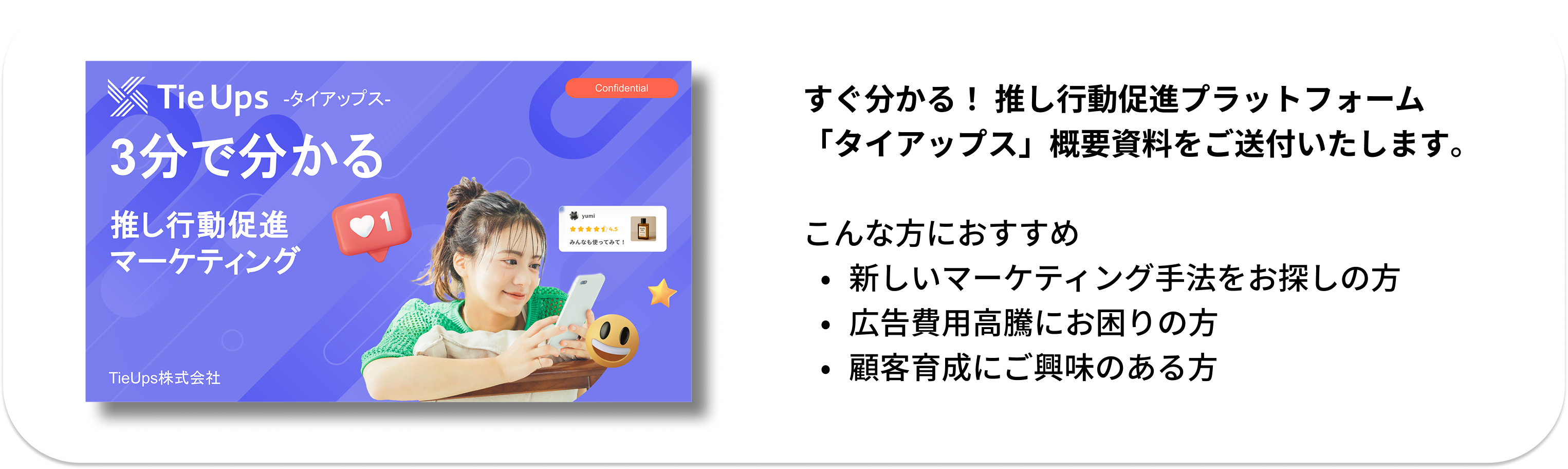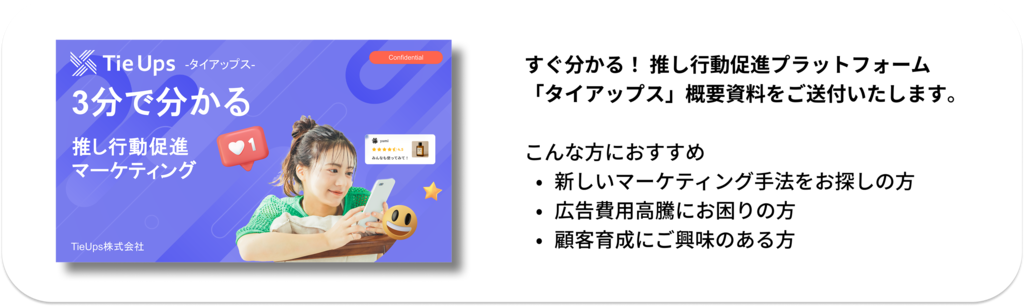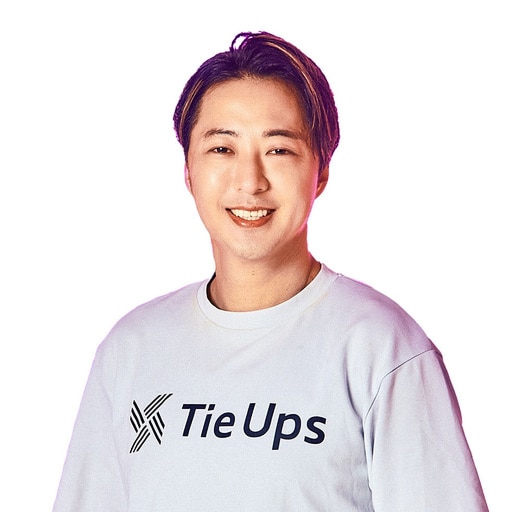SEOからAIOへ―AI時代の企業マーケティング戦略と生存条件
〜コミュニティ×AIで築く新しい顧客関係〜
TieUps株式会社 CEO の小原史啓です。
インターネットの情報流通の構造が、いま大きく変わろうとしています。
長年マーケティングの世界で常識とされてきた「SEO(検索エンジン最適化)」のルールが、AIの台頭によって根本から書き換えられようとしています。
その変化のキーワードが AIO(AI最適化)です。
今回は、その背景と企業に求められる新しい戦略、そして私たちTieUpsが提案する解決策について、オンラインコミュニティスタートアップを経営する私・小原が感じたことを書き留めます。
AIOとは何か――SEOからのパラダイムシフト
マーケティング関係者なら「SEO」という言葉には馴染みがあると思います。SEOとは、Googleをはじめとする検索エンジンで、自社のWebページをより上位に表示させるための最適化手法です。
一方このAIOという概念は、マーケティングの分野で広がり始めてから、まだ数年しか経っていません。
しかし今年(2025年)、Google検索結果画面にAIによる要約・説明機能(サジェスト)が本格的に導入されました。その結果、情報取得の入口が変わり、個別のサイトページを見なくても、簡単に要点を知ることができるようになりました。実際、一部のサイトではアクセスが7〜8割減というケースも出てきています。
「AIOって何?」と問われたら、私はこう答えます。
SEOが“検索”を最適化する営みだとすれば、AIOは“AIが参照し要約するすべて”を最適化する営みです。
つまり、「AIがどう情報を拾い、どう要約・提示するか」を意識しない限り、企業サイトは良いページを作っても見つけてもらえない時代に突入したのです。こうした事態を背景に、AIOはますます重要なテーマとなっています。

SEOは“点”、AIOは“面”で判断し、全体を要約する
SEOの基本は、個別ページ単位での最適化です。
ユーザーが検索する言葉と企業が発信する言葉との間にズレが生じないように調整し、検索結果にヒットさせるという戦略です。加えて、検索したユーザーにとって記事の内容が有益か、サイト内での滞在時間など、さまざまな指標も評価に含まれます。
ユーザーが検索するキーワードと企業の情報発信を合わせ込み、そのページ自体の滞在時間や価値を評価してもらう――そんな積み上げ方をしてきました。
しかし、AIOの世界では事情が一変します。
AIは、単一ページではなく複数の情報源をマージし、要約して提示します。つまり、特定のページだけを磨けばいいわけではなく、インターネット上のあらゆる情報――記事、レビュー、SNS投稿など第三者による広範な情報も対象となる――を総合的に評価する構造になっています。
企業が1つの質の高いページを作成するだけでは不十分で、インターネット上に点在する様々な情報を、AIにとって評価しやすい形で整える必要があるのです。
これにより、企業は「情報の全体最適化」を迫られることになり、SEOと比べてAIO対策は難しいとされています。
この全体最適化こそがAIOの難所です。自社サイトだけでなく、第三者の口コミや外部メディアの記事まで、幅広い情報経路でポジティブな評価を得なければならないのです。

鍵は「2%の発言顕在層」――98%を動かす少数
このような状況に対しては、ネット全体に散在する情報の底上げが必要となります。一見するとこれは不可能に思えるほど困難な課題に見えますが、私たちはある重要な数字に注目することで、この課題に対する解決策を見出しています。
有名なマーケティング理論にパレートの法則がありますね。「結果の8割は、全体の2割の要素によって生み出される」という理論です。
しかし、AIOの文脈で私が重視しているのは「2% 対 98%」です。
これは、インターネット上で発言する消費者は全体の約2%しかいないという現状を表しています。
*1:インターネット上で積極的に情報発信する発言者は非常に限られており、いわゆる「発言するのはごく少数派」であることが知られています。例えば、インターネット上のコミュニティでは「1%ルール」として、ごく一部の人だけがコンテンツを作り、残り99%は閲覧・消費にとどまるとされます(経験則)。また、Pew Internet & American Life Projectの調査によれば、アメリカにおいて「ブログを書いている人」は全体の約2%にすぎないという結果もあります。
このように、ネット上で「声を上げる」のは限られた少数であり、その構造を理解することは、世論やマーケティングの解釈においても重要です。
購入後にSNSやレビューへ投稿する“発言者”は概ね2%。そのごく少数の人々による投稿が、残り98%の情報体験を形づくることになります。
その事実を踏まえて、私たちがやるべきことは何か。
それは、2%の発言顕在層”を発見し、関係性を育て、自然な行動へ導くことです。
もしこの「発言顕在層」にポジティブな体験や情報を提供できれば、その影響力は圧倒的です。AIO対策の本質は、まさにこの層との関係構築にあります。

TieUpsが提案する、AIO時代の新戦略
インターネット上での発言モチベーションが高く、SNSやコミュニティといった交流の場で積極的に発信している層に効果的にアプローチする方法は何か。
TieUpsが提案する施策は、企業やブランドが独自のコミュニティを構築し、情報発信力の高い層を集め、ポジティブな発信を促進するというものです。
その具体的な施策の一つが「推し行動促進マーケティング」(※1)です。
(推し行動促進マーケティング詳細についてはこちらの記事をご覧ください)
これは、コミュニティ内でユーザーが報告する情報や活動内容をAIがスコア化し、行動を促進する仕組みです。“行動”に着目するというのがAIO施策のポイントになります。TieUpsでは、顧客起点でブランドを自然に応援する行動を推し行動と呼んでいます。
例えば、飲料メーカーのブランドにおいて、ただ缶で飲むのではなく、氷を入れて飲むといった工夫が味わいを高め、さらにその体験が口コミとして広がる場合、そうした行動を推し活動として位置づけます。
そして、コミュニティ内のクエスト機能を使って、ユーザーに推奨行動と結びついたチャレンジを促します。TieUpsのクエスト機能は、ゲーミフィケーションの要素を取り入れており、ユーザーが楽しみながら発信できる仕組みになっています。その成果をスコア化・可視化することで、よりコミュニティ内でのアクティブな活動とコミュニティ外での自然な行動を促すのがこの取り組みの特徴です。
従来のコミュニティでは、ユーザー同士の盛り上がりやブランドへのエンゲージメントを測る指標がないことが課題のひとつでした。
アクションスコアの導入により、企業にとっては定量的な評価をしながら顧客との深い関係を構築し、自然なUGCを期待できること、ユーザーにとってはコミュニティ内での投稿ハードルが下がり気軽に交流を楽しめることが大きなメリットです。

一過性の対策は、AIには通用しない
現在、AIOは発展途上にあり、それに伴って「AIO対策」も多く登場しています。中には、報酬を支払って消費者に無理やり口コミを書かせたり、BotやAIを活用して大量にレビューを生成したりするような、短期的な「見せかけ施策」も見受けられます。
これはかつてSEO黎明期に頻繁に行われていた手法と同様ですが、技術の進化とともにそのような小手先の施策は無効化されていきます。仮に短期間で効果が出たとしても、数年後にはそのしわ寄せが来るでしょう。そしてなにより、ブランド毀損に繋がるリスクもあります。
本当に必要なのは、正当で持続可能な顧客とのリレーション構築です。
良い製品・良い体験をつくる → 推奨行動を設計する → 発言顕在層と持続的な関係を築く
特にインターネットで積極的に活動する層と密接に関わり、商品やブランドへの理解と愛着を時間をかけて育てる――これこそがAIO時代を生き抜く企業にとって重要な考え方です。
AIO時代の勝ち筋は「コミュニティ×AI」
最後に、今後AIO領域がどのように進化していくのか、また企業のマーケティング活動がどう変化していくのかについて述べたいと思います。
今後は、AIが単なる検索補助ではなく、生活者の意思決定プロセス全体に深く入り込み、複数の情報源を統合して提示する「情報のハブ」として機能していきます。
これにより、従来のSEO的な個別ページ最適化は限界を迎え、企業はネット上に分散する自社関連情報の総合点を意識した施策設計が不可欠になります。
またそれに伴って企業は、自社サイトや公式発信だけでなく、口コミ、レビュー、SNS、コミュニティなど、外部環境に広がる生活者の声を戦略的にデザインすることが求められます。
特に発言モチベーションの高い少数の顧客層とどのように関係を築き、推奨行動を増幅させるかが、AIO時代の競争優位を左右します。
長期的視点での顧客リレーションの在り方を見直し、単なるテクニカルな対策にとどまらず、生活者との継続的な関係構築を行うことこそが、AIO時代における最適なマーケティング戦略だと考えています。
とはいえ、AIOに関する取り組みは発展途上であり、「具体的にどう取り組めば良いか分からない」というお声も少なくありません。
TieUpsではコミュニティ運営を通じて、顧客との企業の深い関係構築の機会を提供しています。
コミュニティ運営にご興味をお持ちの方、AIO対策を本格的に進めたいという企業の皆様には、ぜひご相談いただければと思います。

(※1)用語補足:「推し行動促進マーケティング」
コミュニティとAIを用いて、ブランドにとって望ましい顧客の推奨行動(投稿・参加・紹介・共創など)を定義し、内容ベースで評価(AIスコアリング)し、運用プログラムで継続的に促進するための仕組み。従来の量的KPI(件数・到達)に偏らず、文脈と質を評価軸に含める点が特徴です。